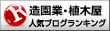おもしろい写真がみつかったので載せてみます。上の写真は5年前に1,000円で買った黒松の盆栽です。
針金が巻いてあるのは盆栽ではめずらしくないのですがずっと放置してると幹枝に食い込んでしまいます。さらに放置すると木に飲み込まれてしまいます。
針金が飲み込まれる寸前なのを強引に取り除いた後の画像です。当時、「この傷はちょっと厳しいな」と思ったのですが、5年経ちなんとか傷がふさがりつつあります。
ちなみに傷口が一周ぐるりと回ってるわけではなく水の通り道が僅かながら繋がってるから上の部分は枯れなかったのです。


お次は庭木の黒松の強剪定後の太枝の癒合の進み方を見てみましょう。上の写真は2年前の2018年4月末にみどり摘みを兼ねて太い枝を切った時の画像です。かなり強引な切り方ですね(汗)

2年後の下の枝
こちらは微妙なところ、右からは傷が巻いてますね。

2年後の上の枝
こちらは駄目(失敗)ですね。まったく傷口が治ってません。こういう切り口は見た目が悪いのはもちろん、将来腐りが入る可能性もあるわけです。この傷口は水がたまらないので大丈夫っぽいですが・・・

ここも結構強引な切り方してますが、よい感じに傷が巻いてますね^^

これが一番ベストな癒合の仕方です。切り口から綺麗に傷が巻いてますね~。これは適切な位置で枝が切れた証拠です。
ちなみに適切な位置とはブランチカラーと枝との境目です。くわしくは「ブランチカラー」と検索してみてください。
松の場合、切り口から松脂が染み出てくるので癒合剤は塗らなくてよいと思いますが心配なら定番のトップジンMとかを塗るのもよいと思います。一般的に塗ったほうが傷の治りが早いです。
ちなみに太枝を切った時に時期や樹種によっては切り口から水が吹き出る場合があるのですが、トップジンは水を止める力はありません。大概自然に止まります。
樹勢の強い木ならほかっといても大丈夫ですが弱ってる木は太い枝は切らないほうが無難です。切った場合は癒合剤を塗ってあげてくださいね。